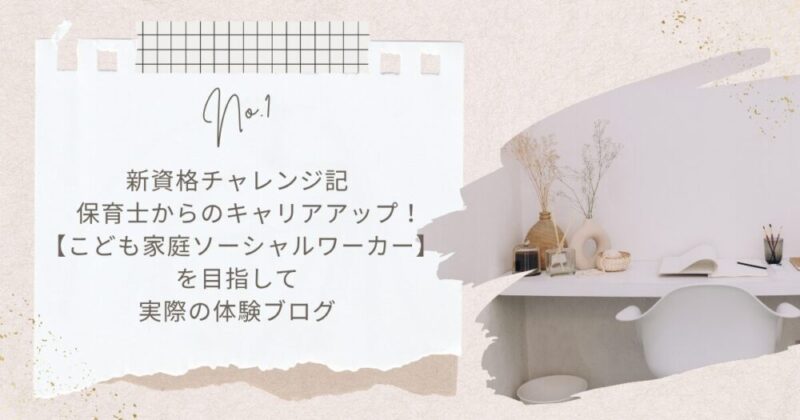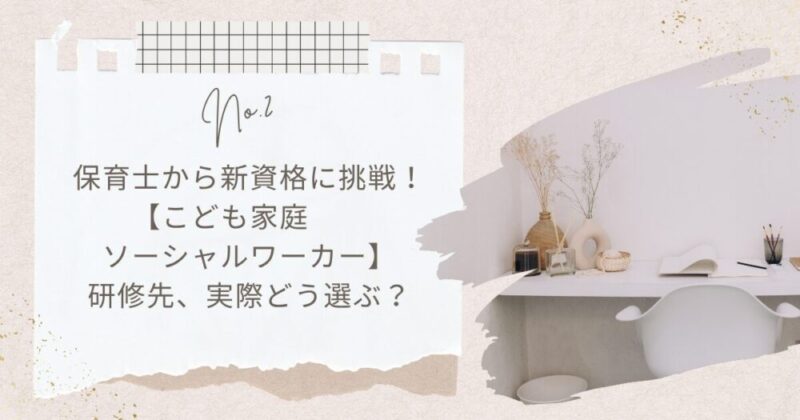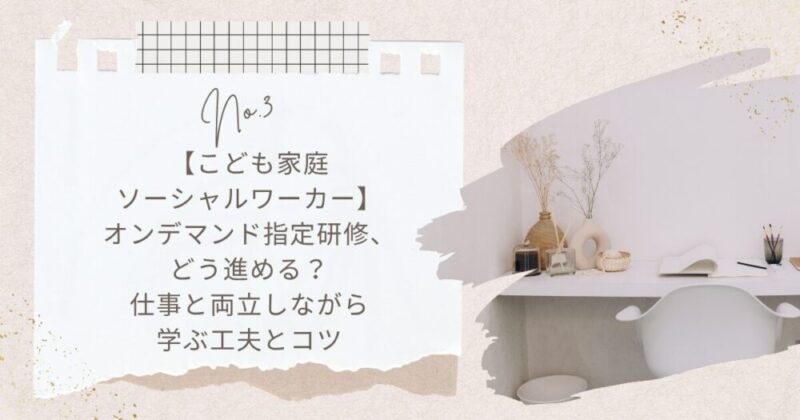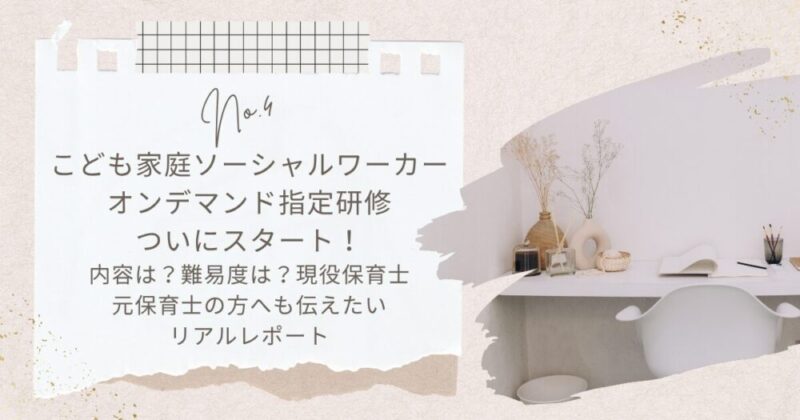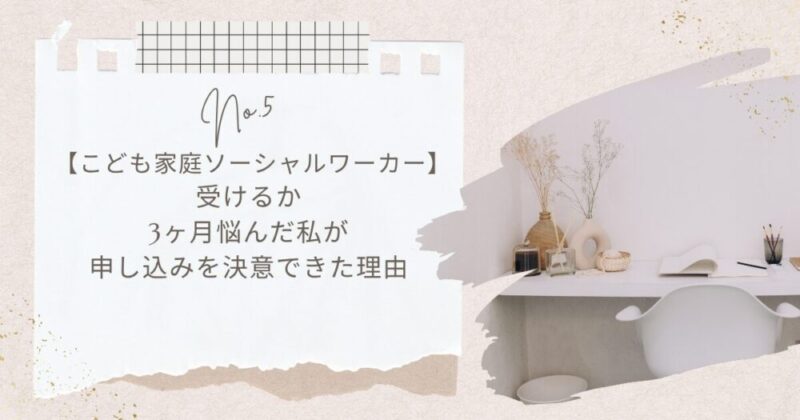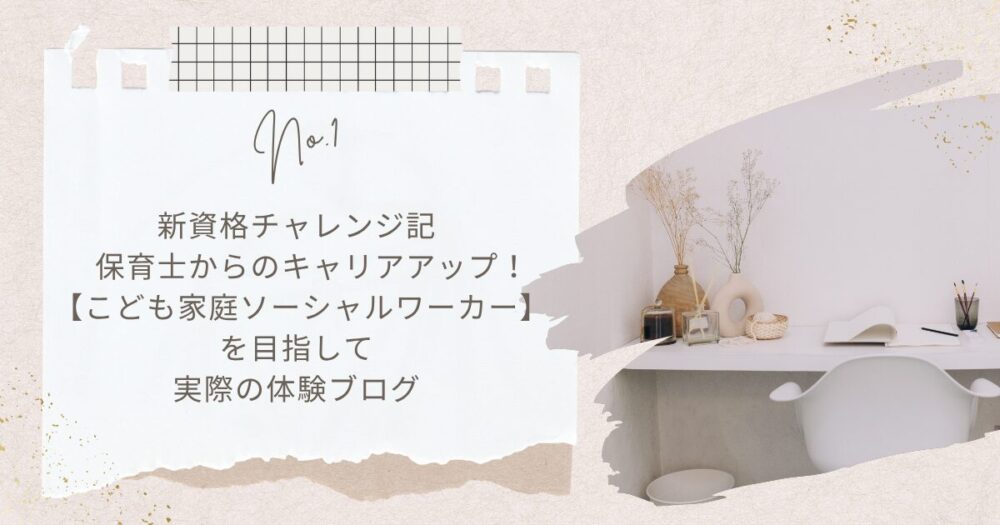こんにちは、れいです。
私はこれまで保育士として10年以上こどもや保護者と向き合ってきました。現場では毎日が学びと発見の連続で、大変だけれどやりがいのある仕事でした。
「もっと、子どもと家庭を支える知識を増やしたい」
その答えの一つとして私がたどり着いたのが、2024年に誕生した新しい福祉資格「こども家庭ソーシャルワーカー」でした。
このブログでは、現場経験者だからこそ感じたリアルな不安や疑問、費用の壁、学び直しの葛藤、受験までの手続きなどを、すべて本音で発信していきます。
こども家庭ソーシャルワーカーとは?【新設資格の概要】
「こども家庭ソーシャルワーカー」は、2024年4月にスタートした新しい福祉資格です。
この資格ができた背景には、以下のような深刻な社会課題があります:
- 児童虐待の増加
- 家庭内での孤立
- 経済的困難による育児困難
- 保育士だけでは対応しきれない家庭支援の必要性
こうした背景の中で、より専門的な知識と実践力をもった支援者が求められるようになりました。
そこで国が立ち上げたのが、この**「子どもと家庭の福祉のプロ」を育てる資格制度**なのです。
保育士でも目指せる!取得ルートと条件
こども家庭ソーシャルワーカーの資格は、以下の4つのルートから取得できます。
- 第1号ルート:社会福祉士または精神保健福祉士+2年以上の相談援助経験
- 第2号ルート:上記資格あり・相談援助時間が半分未満だが、2年以上の経験あり
- 第3号ルート:福祉士資格なし+4年以上の相談援助経験
- 第4号ルート:保育士資格+保育所等で4年以上の相談経験 ← 私はこちら!
これまでの保育士経験がキャリアに直結するのは、とてもありがたいポイントでした。
受講・試験の流れとリアルな費用
資格取得には、以下のステップがあります:
- 受講要件の審査(20,000円)※該当していなくても戻ってきません。
- 指定研修の受講(第4号ルートの場合、ソーシャルワーク研修を含め約100.5時間以上)
- 資格認定試験の受験(25,000円)
実際にかかる費用は以下の通りです(私の場合):
| 項目 | 費用(目安) |
|---|---|
| 受講要件審査 | 20,000円(税込) |
| 研修受講料 | 約400,000円〜 ※ |
| 試験受験料 | 25,000円(税込) |
※研修費用は講座を提供する大学や機関によって差があります。私が申し込んだところは高めでしたが、その理由も今後ブログで紹介します。
保育士からの転職・キャリアアップとしての魅力
保育士として働く中で感じたのは、「子どもだけでなく、家庭全体を支える視点」の重要性です。
保育園での対応だけでは解決できないことも多くありました。
そんなとき、福祉の視点とスキルがあれば、もっと寄り添った支援ができたのではと思う場面が何度もありました。
「こども家庭ソーシャルワーカー」は、保育士キャリアの延長として、家庭に寄り添う新しい専門職の道を開いてくれる資格です。
保育現場を離れてから挑戦を決意
今は保育現場を離れ、別の仕事をしながらのチャレンジです。
そのため、こども家庭庁の研修補助制度や現役職員向けの支援制度は利用できません。
経済的な負担も大きく、「自分に本当にできるのか」と何度も迷いました。
ですが、今だからこそ、「やるなら今」と思い切ることができました。
私の場合は、保育現場にいたら、研修のための休みを取るのは難しかったかもしれません。
転職した今の環境だからこそ、学ぶ時間を確保できる――これも一つのタイミングの巡り合わせだと感じています。
これからのブログで発信する内容
以下のようなテーマで、リアルな体験をわかりやすく発信していきます:
- 申し込み手続きの流れや注意点
- 保育士ルートでの受講内容や時間の捻出方法
- 講義の雰囲気やモチベーション維持のコツ
- 資格試験の内容と対策(今年合格目指して頑張ります!)
- 実習の体験レポートや感想
- 費用のまとめ
「何かを始めたい人」の背中を押せたら
このブログは、「子ども家庭ソーシャルワーカーを目指す人」だけでなく、
- キャリアに悩んでいる保育士さん
- 福祉資格の取得を検討している人
- 一歩を踏み出したいけど迷っている人
そんな方々にも、少しでも参考になるようなブログにしたいと思っています。
私の記録が、どこかの誰かの「やってみよう」に繋がるなら嬉しいです。
SNSでも発信中!ぜひフォローしてください
📷 Instagram:資格勉強の息抜きや日常の小ネタ
🐦 X(旧Twitter):講義の感想やリアルな悩みもつぶやいています
\更新通知も届くので、ぜひフォローしてくださいね!/
まとめ:新しい福祉の形に、保育士の経験を活かして挑む
「こども家庭ソーシャルワーカー」は、保育士からのキャリアアップ・転職の一つの選択肢になるの資格です。
情報が少ない今だからこそ、リアルな体験を発信し続けていきます。
今後の更新も、ぜひ楽しみにしていてくださいね。